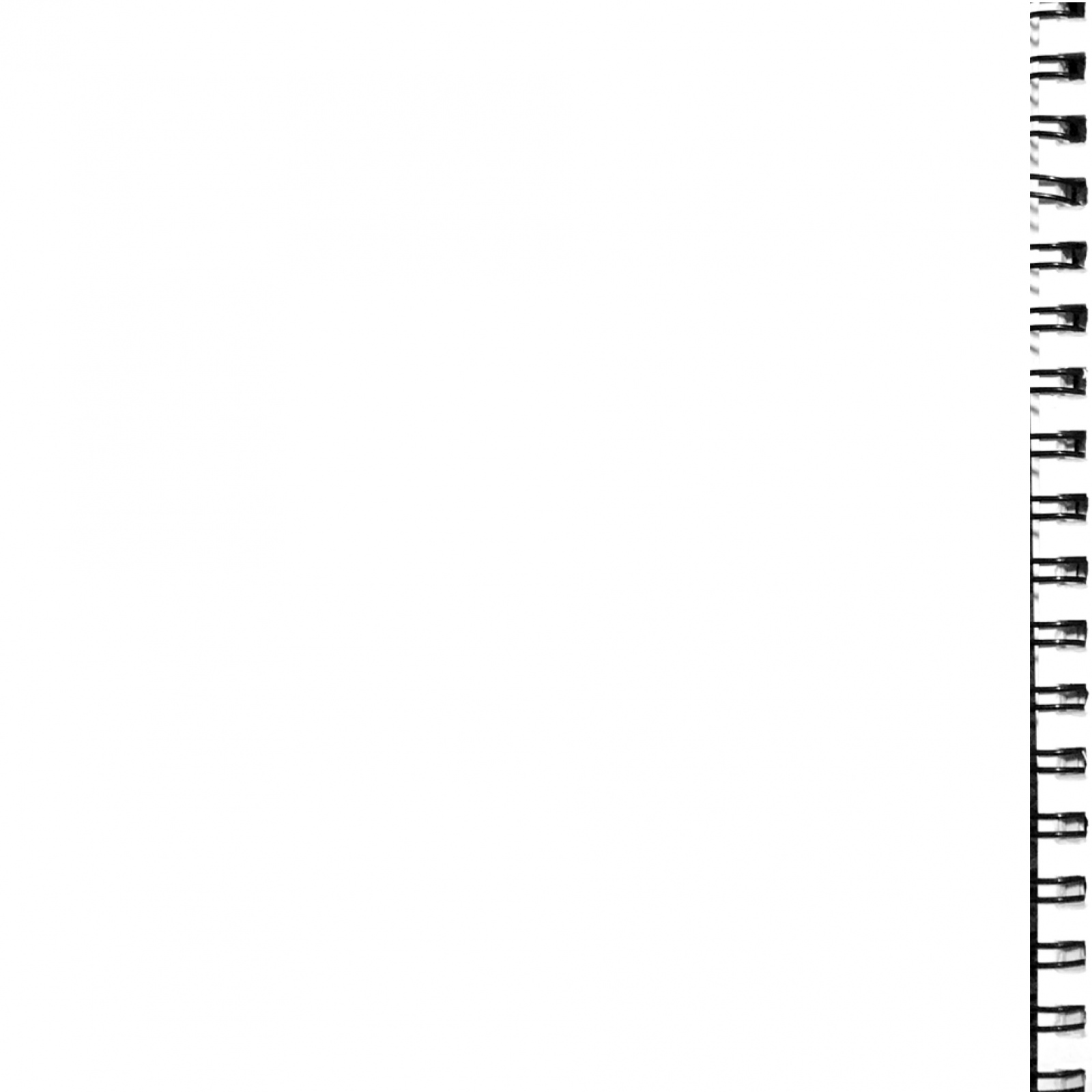25時44分、青梅街道沿い、安アパートメント。
うだるような、しつどのたかいこのへやの、
せまいパイプベッドにおとこふたり。
なんなんだこれは。
とりあえず引っ越したその日に間に合せで買った大して光を遮る気もないカーテンが、
街道沿いのテールランプを規則正しく映し出す。
うるさいバイクがまた1台。
テールランプを引っさげて駆け抜ける。
眠らない街。サイレンの音。道路清掃車の通る音。酔っ払いの笑い声。
あー、こんな物件借りるんじゃなかったな。
上京して大学で出会ったこいつは、やれ終電を逃したとか、酒を飲みすぎたとか理由をつけては家にずかずかと上がり込んできて、俺の服を勝手に着てベッドを占領する。
そしてすぐに寝息を立てる。
そんな日々が続いていた。
不思議と苦しくない時間だった。
うだるような、窮屈な部屋で、唯一酸素を与えられるような、息ができる時間だった。
明け方まで飲み明かした俺たちは始発を待っていた。
眠い眠いと欠伸ばかりする俺とは正反対にキラキラと目を輝かせるこいつは、
朝焼けって、1日の締めくくりって感じでなんか切ないよね〜
と紫かかった空を眺めながら呟いた。
朝焼けが締めくくりなら、
今からうちに帰ろう。帰って夕焼けが来るまで寝よう。
そう言って初めて俺から家に誘った。
−−−うだるような、しつどのたかいこのへやの、
せまいパイプベッドにおとこふたり。
なんなんだこれは。
ねぇ。
か細いこえが聞こえた。
ねぇ、ぼくと君がキスしたら何かが変わっちゃうかな?
背中越しに聞こえた、少し震えた声だった。
俺は振り返らなかった。
代わりにそっと手をとって、
何も変わらない、いつも通りだ。
明日も明後日も一年後もその先も。と。
…ありがと、嬉しいよ。
ぎゅっと握り返された手はどこまでも暖かくて。
俺はこの先こいつとセックスはしないだろう。
友達の先に恋人があって、そこに欲情というものが生まれて初めて恋愛というのなら、これは恋愛なんて甘ったるいものなんかでは無い。
友情だから永遠に続くって漠然と信じられる俺たちはまだ子供だろうか。
せまいパイプベッドにおとこふたり。
なんなんだこれは。
とりあえず引っ越したその日に間に合せで買った大して光を遮る気もないカーテンが、
街道沿いのテールランプを規則正しく映し出す。
うるさいバイクがまた1台。
テールランプを引っさげて駆け抜ける。
眠らない街。サイレンの音。道路清掃車の通る音。酔っ払いの笑い声。
あー、こんな物件借りるんじゃなかったな。
上京して大学で出会ったこいつは、やれ終電を逃したとか、酒を飲みすぎたとか理由をつけては家にずかずかと上がり込んできて、俺の服を勝手に着てベッドを占領する。
そしてすぐに寝息を立てる。
そんな日々が続いていた。
不思議と苦しくない時間だった。
うだるような、窮屈な部屋で、唯一酸素を与えられるような、息ができる時間だった。
明け方まで飲み明かした俺たちは始発を待っていた。
眠い眠いと欠伸ばかりする俺とは正反対にキラキラと目を輝かせるこいつは、
朝焼けって、1日の締めくくりって感じでなんか切ないよね〜
と紫かかった空を眺めながら呟いた。
朝焼けが締めくくりなら、
今からうちに帰ろう。帰って夕焼けが来るまで寝よう。
そう言って初めて俺から家に誘った。
−−−うだるような、しつどのたかいこのへやの、
せまいパイプベッドにおとこふたり。
なんなんだこれは。
ねぇ。
か細いこえが聞こえた。
ねぇ、ぼくと君がキスしたら何かが変わっちゃうかな?
背中越しに聞こえた、少し震えた声だった。
俺は振り返らなかった。
代わりにそっと手をとって、
何も変わらない、いつも通りだ。
明日も明後日も一年後もその先も。と。
…ありがと、嬉しいよ。
ぎゅっと握り返された手はどこまでも暖かくて。
俺はこの先こいつとセックスはしないだろう。
友達の先に恋人があって、そこに欲情というものが生まれて初めて恋愛というのなら、これは恋愛なんて甘ったるいものなんかでは無い。
友情だから永遠に続くって漠然と信じられる俺たちはまだ子供だろうか。